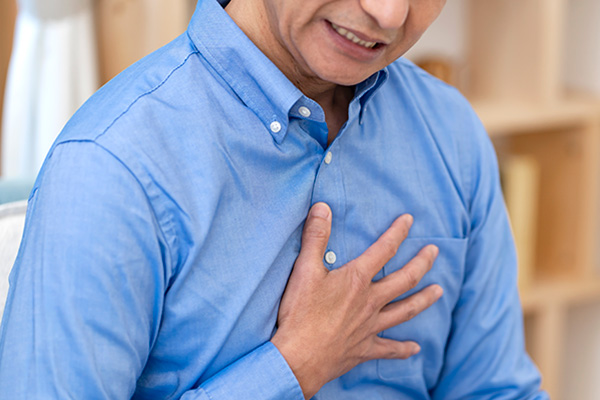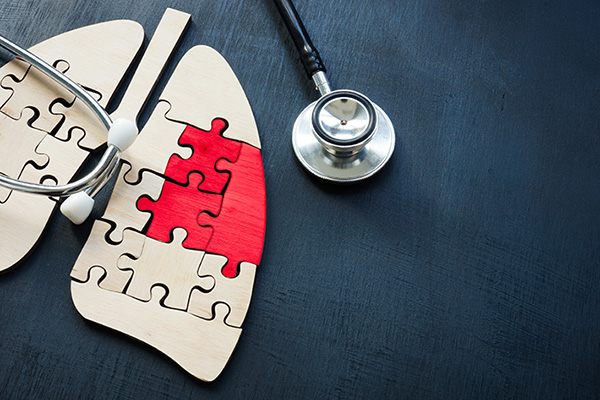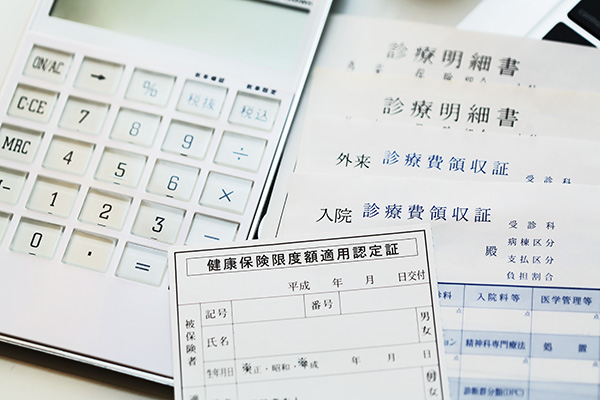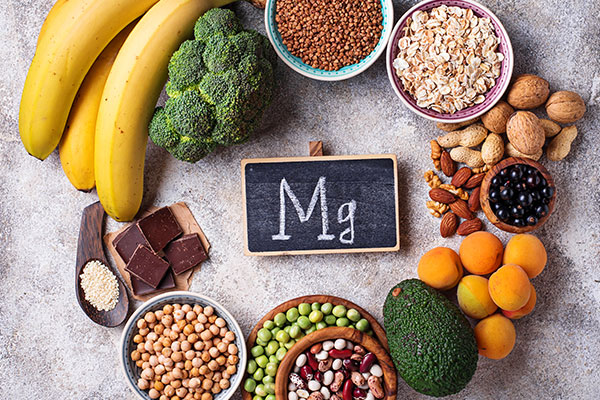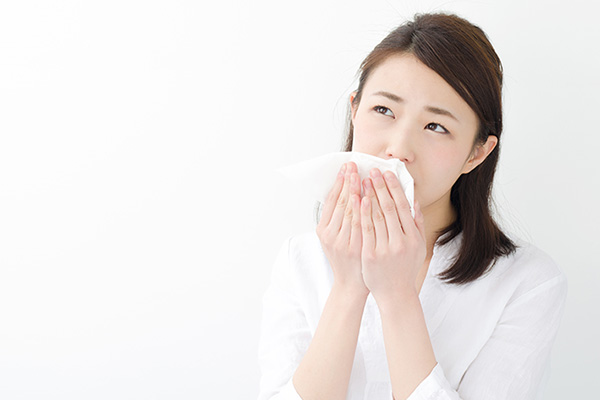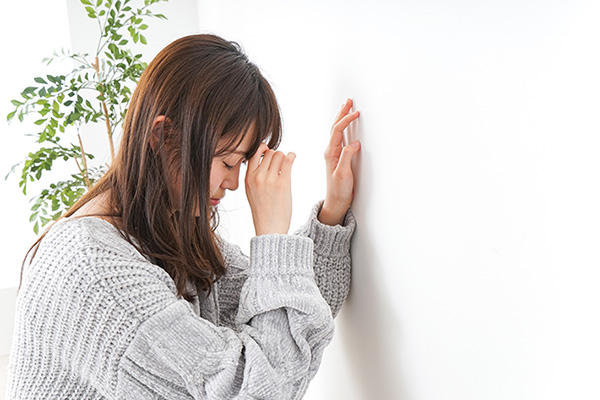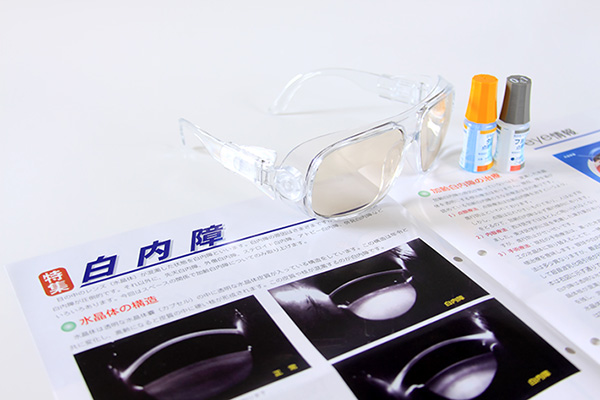「人の名前がなかなか思い出せない」「部屋に来たら何が必要だったか忘れてしまった」――。加齢とともに、「物忘れ」が気になる場面が増えてきます。「もしかしたら認知症?」と心配する人もいるかもしれませんが、さまざまな原因が考えられます。「物忘れ」と「認知症」の違い、「物忘れ」の原因、脳を活性化するポイントなどを、メモリークリニックお茶の水理事長の朝田隆さんにお聞きしました。
物忘れが気になるなら、
まずはチェックしてみましょう
物忘れにもいろいろあります。まず、どのようなことを「忘れる」のか、チェックしてみましょう。
- □ 1人の名前が出てこない。
- □ 2「あれ」「これ」を多用する。
- □ 3物を取りに行ったのに、移動したら何をしにきたか忘れてしまう。
- □ 4会議など重要な約束の予定を忘れる。
- □ 5料理の味付けが下手になった。
- □ 6ガスや水道の閉め忘れ、電気の消し忘れなどが多くなった。
- □ 7何を食べたかではなく、食事をしたことそのものを忘れることがある。
- □ 8車の運転中に方向がわからなくなる。
- □ 9ぐっすり眠れない、眠りが浅い。
- □ 10やる気が出ない、気分が落ち込む。
- □ 11集中力がない。
- □ 12数分、記憶が飛ぶことがある。
- □ 13意識が一時的にもうろうとする。
心配のない物忘れと
認知症かもしれない物忘れ
単なる「物忘れ」と、認知症の「物忘れ」とは違います。先のチェックリストの1、2、3のように、ある特定の瞬間、思い出せなかったとしても、ヒントが得られたときや、ちょっとしたはずみで思い出すことができるなら、心配のない「物忘れ」、つまりは単なる“度忘れ”です。認知症の可能性は低いといえるでしょう。
単なる「物忘れ」はふと忘れてしまって思い出すのが困難な状態、認知症の「物忘れ」はあることを覚えようとしても覚えられない状態をいいます。
認知症に見られる「物忘れ」は、例えば、結婚式に出席したのに何を食べたか、誰が挨拶をしたかといった部分的なことを忘れてしまうのではなく、結婚式があったこと自体を忘れてしまう状態です。エピソード全体を捉えられない「エピソード記憶の障害」が特徴です(→ チェック7)。
また、記憶以外の不注意や失敗が多くなる、距離感がわからなくなる、といったことも、認知症に見られる特徴の一つです(→ チェック5、6、8)。
また、単なる物忘れとは少し異なり、重要な予定を忘れてしまう「展望記憶」というものがあります。例えば、「今日は18時から会議がある」ということを朝から意識していて、15時くらいまで覚えていたのに、気づくと18時半に。そこで「しまった、18時から会議だったのに!」と思い出すのです。すべてを忘れてしまうわけではありませんが、特定の時間帯の予定や行動をタイミングよく思い出す力が弱くなるケースです(→ チェック4)。
年齢を重ねれば誰でもある程度、脳の機能が衰えてきます。40代後半以降になれば多かれ少なかれ経験することで、「物を片づけた場所を忘れることがある」というレベルであれば、即問題というわけではありません。しかし、「物を片づけたこと自体を忘れる」ような物忘れがあまりにも増えてきたら、念のため「物忘れ外来」を受診するとよいかもしれません。
また、ちょっとした物忘れは誰にでもあることとはいえ、加齢による物忘れと認知症とは、全く別物ともいえません。不注意や小さな失敗は、いわば良性と悪性の中間のようなもので、健常な人の物忘れでも、軽度認知障害(MCI※)でも同じような症状が見られるため、初期には区別がつきにくいのです。
異常に早く気づくためには、「記憶」だけが問題なのではなく、「注意」を四方八方に向ける収容力(キャパシティー)と正確さ(タイミング)がポイントであることを知っておくとよいでしょう。
※軽度認知障害(MCI):正常と認知症の間のグレーゾーン状態の認知症予備軍。4〜5年で約40~50%が認知症に進むとされる。早期発見、早期治療で回復したり、発症が遅延したりするという研究報告もある。
物忘れの背後に
病気が隠れていることも
物忘れの背後に何らかの病気が隠れていることもあります。その一つがうつ病です。うつ病の場合は気分が落ち込む以外に、注意力が落ちる、集中できないといった症状があります(→ チェック9、10、11)。一度記憶したものを忘れるというよりは、そもそも覚えていない可能性があります。
また、意外に知られていない原因に、「てんかん」もあります。「てんかん」というと、子どもに多く、けいれんを起こして意識を失う病気と思われがちですが、けいれんを伴わず、数分間、意識がもうろうとなり記憶がなくなる発作を起こす症状もあります。この発作は60代以降に多く、アルツハイマー病の前兆であるケースもみられます(→ チェック12、13)。
うつ病やてんかんは、薬物療法などの適切な治療で改善する可能性が高い病気です。うつ病でしたら精神科や心療内科を、てんかんでしたら神経内科で検査を受診することをおすすめします。
そのほか、夜間の睡眠の質が悪いために日中ぼーっとしてしまい、うっかり物忘れをすることもあります。うつ病などで眠れない、睡眠時無呼吸症候群で自分では寝たつもりでも実は眠りが浅いという場合も考えられます。
一般に、よく眠って気分が冴えているときの方が記憶力がよく、徹夜明けでは複雑なことは覚えられないものです。集中や記憶といった脳の働きを健やかに保つには、やはり睡眠の質・量が保たれていることが基本です。物忘れの最大の要因は加齢ですが、睡眠不足などで集中力が低下したり、メンタル的な不調があれば、度忘れが多くなることも考えられます。物忘れの背後に病気が隠れていないか、生活を見直すことで改善するのか、見極めることが大切です。
脳を活性化し、
物忘れを防ぐには?
脳を活性化し、物忘れを防ぐためにできる対策はあるのでしょうか。
まずは、運動する習慣をつけることです。運動をするとBDNF(脳由来神経栄養因子)という脳の成長にかかわる物質が分泌され、脳に栄養を送る血管や神経の生成や成長を促進し、脳が

例えば、誰かと会話ができるくらいの速さで歩くと、効率のよい有酸素運動になるといわれています。10分で通常の90分程度の脳エネルギー消費量になるといわれていますので、脳の血流も増えると考えられます。
「脳トレーニング」にもいろいろありますが、Web系のものが効果が高く、研究で成果を報告されたゲームもあります。そのほかにも「瞑想」の有効性が科学的に確かめられ、注目されてきています。
「人との交流」もとても重要です。人にはミラーニューロン(他者の行動をまねる機能を持つ神経細胞)や顔細胞(目、鼻、口の順で顔として認識する神経細胞)という、顔に特化した機能を持つ細胞が生まれながらに備わっています。家に閉じこもる生活が続けば認知機能は低下するし、反対に社会に出て人と交流していくことで脳が活性化するというのも、自然なことなのです。
健康的な生活のためには、良い食習慣もかかせません。肥満や糖尿病といった生活習慣病は認知症のリスクとなります。
脳機能を維持する面でも食事や運動、睡眠などの基本的な生活習慣を良くすることがベースになると考えてよいでしょう。
こうした良い習慣を、若い頃から続けていくことが大事です。「習慣とは努力せずにぴったり同じことを繰り返せること」と朝田さんは言います。努力せずできるようになるまで、一時期努力して続けることが必要であり、認知症になってからではできないのです。だからこそ、よい習慣づくりを一日も早く始め、意志を持って長く続けていきましょう。
最後に、冒頭のチェックリストの結果です。あなたの物忘れは大丈夫ですか?
項目1、2、3にチェックがあった人は、心配する必要はないでしょう。4、5、6に加えて、他の項目にも当てはまるようなら、物忘れ外来など該当する科を受診すると安心です。
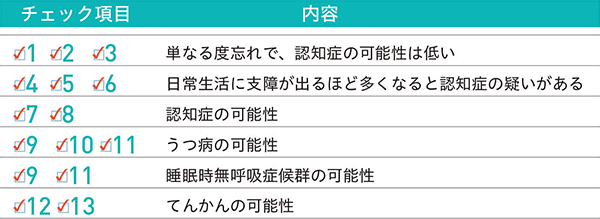
1982年 東京医科歯科大学医学部卒業。1991年 医学博士(山梨医科大学)。1995年国立精神・神経医療研究センター武蔵野病院精神科医長、2001年筑波大学臨床医学系精神医学教授、2014年東京医科歯科大学医学部附属病院特任教授。2015年4月 筑波大学名誉教授、メモリークリニックお茶の水院長。
著書に『まだ間に合う! 今すぐ始める認知症予防 軽度認知障害(MCI)でくい止める本』(講談社)、『誤診症例から学ぶ 認知症とその他の疾患の鑑別』(医学書院)など。