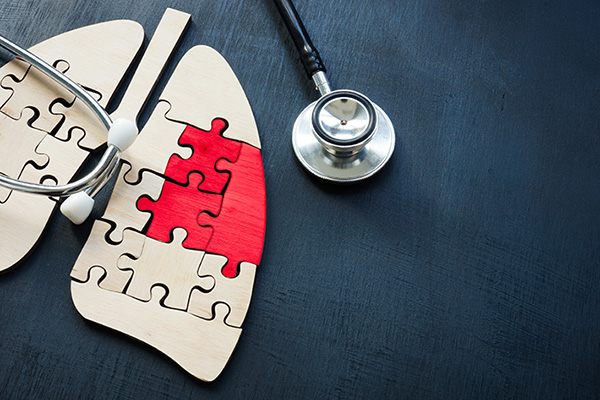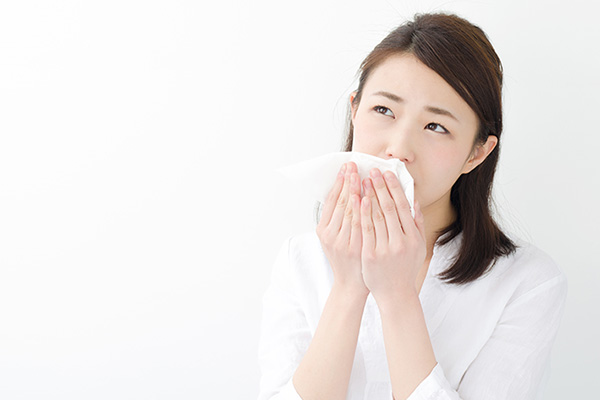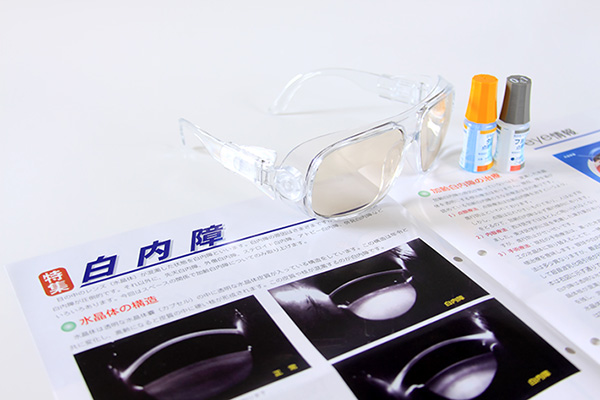かつてはがんの
胃がんは「減っていくがん」
80代がピークで高齢化
胃がんは、胃の内側を覆う粘膜に発生します。がんが進行するにしたがって胃の外側へと深く進んでいきリンパ節転移や遠隔転移(他臓器への転移)となります。がん細胞が粘膜または粘膜下層にとどまっているものを「早期胃がん」、それ以上に深く達しているものを「進行胃がん」といいます。胃がんの発症は50歳を過ぎると増え始め、ピークは80代と高齢化しているのが特徴です。
国立がん研究センターによると、胃がんの罹患数は約12万4000人で第3位(2020年)、死亡数も約4万2000人で第3位(2019年)であり、上位を占めるがんと言えます。一方で、人口の高齢化の影響を除いて年齢調整した罹患率と死亡率は低下傾向にあります(図1)。
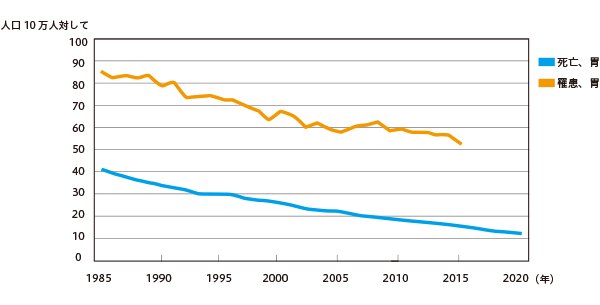 資料:研究開発法人国立がん研究センターがん対策情報センター
資料:研究開発法人国立がん研究センターがん対策情報センターCenter for Cancer Control and Information Service, National Cancer Center, Japan
(注)基準人口は昭和60年(1985年)モデル人口を使用
胃がんの初期にはこれといった自覚症状がなく、かなり進行していても症状がない場合もあります。胃の痛み・不快感・違和感、胸やけ、吐き気、食欲不振といった胃がんの代表的な症状は、胃炎や胃潰瘍でも見られます。医療機関を受診して偶然、胃がんが見つかることがありますが、こうした症状で胃がんだった場合は進行胃がんである可能性が高いです。
進行胃がんの中には、胃の壁を硬く厚くさせながら広がっていく、「スキルス胃がん」(スキルスとはギリシャ語で「硬い腫瘍」の意味)があります。比較的若い女性に見られ、進行が早く、早期診断が難しく治りにくいがんです。
ピロリ菌感染で胃粘膜の萎縮が進むと
胃がんのリスクが高くなる
胃がんの原因であるピロリ菌は、元来、土壌に生息している細菌です。感染経路としては、ピロリ菌が混入した生活用水(井戸水など)を飲んだ、あるいは感染している親から子への食べ物の口移しが考えられています。ただし、明確な感染経路は未だ不明です。
感染の多くは免疫力が完成していない幼少期(5歳以下)と言われています。日本におけるピロリ菌の感染率は、衛生環境が十分に管理されていない時代に幼少期を過ごした高齢世代で高く、若い世代では低くなっています(図2)。
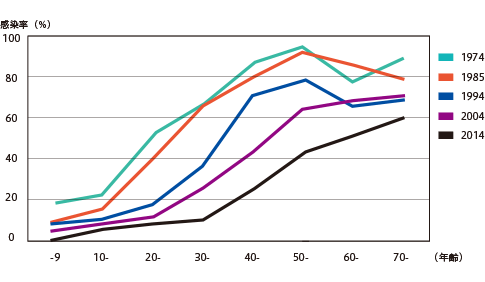 厚生労働省資料「ヘリコバクター・ピロリ除菌の保険適用 による胃がん減少効果の検証について」(国立国際医療研究センター国府台病院 病院長 上村 直実)より
厚生労働省資料「ヘリコバクター・ピロリ除菌の保険適用 による胃がん減少効果の検証について」(国立国際医療研究センター国府台病院 病院長 上村 直実)より
ピロリ菌は胃の粘膜にとりついて炎症を引き起こします。感染が長期間続くと、感染が胃粘膜全体に広がって慢性胃炎(ピロリ感染胃炎)を発症します。慢性胃炎が持続すると胃粘膜が萎縮してやせてしまい(萎縮性胃炎)、さらに進めば胃の粘膜が腸の粘膜のようになる現象(
ピロリ菌感染で胃の萎縮が進むと、胃がんのリスクが上昇することが分かっています。日本人の胃がんの98%はピロリ菌感染によるものです。
一方で、ピロリ菌に感染していても必ず胃がんになるわけではありません。胃がんは、ピロリ菌という初発因子に、塩分過多の食事や喫煙といった促進因子が加わることで、リスクが高まります。高濃度の塩分は胃粘膜を保護する粘液を破壊し、ピロリ菌の感染を持続させると考えられています。
このため、胃がんを予防する際に避けたいのは、塩味の強い食べ物です(辛い刺激物は胃がんの促進因子にはなりません)。なお、初発因子のピロリ菌に感染していなければ、塩分の取り過ぎで胃がんのリスクをさらに高めることはありません。しかし、高血圧など別の成人病のリスクになるため、取り過ぎは体には良くありません。
ピロリ菌を除菌しても
胃がんリスクから解放とはならない
胃がんを発症させないためには、胃がんの原因であるピロリ菌に感染しているかどうかを検査し、感染している場合は早急に除菌することが重要です。
ピロリ菌に感染しているかどうかの最初の検査は一生に一度受ければよく、方法は、診断薬を服用した前後の呼気を集めて診断する尿素呼気試験法、抗体検査(血液や尿で調べる)、抗原検査(便検査で調べる)、胃内視鏡で胃の粘膜を採取して調べる生検などがあります。感染リスクが高い世代では、まずは胃がんの診断が優先されますので、内視鏡検査を強くお勧めします。半年以内の胃内視鏡検査(胃カメラ)で慢性胃炎と診断されれば、保険診療でピロリ菌検査が受けられます。ピロリ菌感染が陰性の方は毎年ピロリ菌感染検査を受ける必要はありません。
ピロリ菌検査で陽性と診断されたら、除菌をしましょう。2種類の抗菌剤と胃酸を抑える薬を1日2回、1週間服用します。その後4週間以降に判定検査でピロリ菌が存在していないことを確認できれば、除菌完了です。それでもピロリ菌が存在していた場合は、再び薬を服用します。除菌は2回目までは保険診療で受けられます。副作用として一時的な皮膚発疹、軟便や味覚異常が出る方がいます。また、除菌薬にはペニシリン系の抗菌薬が含まれていますのでペニシリンアレルギーの方は医師と相談してください。
日本でピロリ菌除菌が保険診療(胃潰瘍・十二指腸潰瘍)として認められたのが2000年、慢性胃炎に適用拡大されたのは2013年です。これにより、除菌する人が増え、年齢調整した胃がんの罹患率は低下しています。ただし、実際の罹患数は横ばいです。これは、高齢化や、ピロリ菌検査と除菌のために内視鏡検査を受ける人が増えて小さながんが見つかっていることが背景にあると考えられています。
除菌によって胃がんのリスクは下がりますが、リスクがゼロになるわけではありません。除菌するまでの間、蓄積された胃のダメージ(胃粘膜の萎縮)は“リセット”されず、リスクとして残ります(炎症は除菌によって改善しますが、萎縮や腸上皮化生などの胃粘膜の変化はあまり戻りません)。ピロリ菌に感染していた年数が長い(ある程度年齢を重ねてからピロリ菌除菌を受けた方)ほど胃がんのリスクは残るため、除菌後も内視鏡検査で胃粘膜の萎縮の程度を確認することが大切です。
感染年数が短い、つまり若い時期に除菌すればリスクを大きく下げることができます。ピロリ菌が引き起こす胃粘膜の萎縮をなるべく早く止めるには、早いうちに除菌するのが望ましいと考えられます。しかし、最近の報告では、粘膜萎縮があまり進んでいない方でも長期間経過観察すると胃がんが発見されているので、やはりピロリ菌除菌後でも安心せずに一定程度の間隔で内視鏡検査を受けることが重要です。
追跡調査の結果、除菌後の発症は10年以内であるため、例えば50歳で除菌した場合、少なくとも60歳までの10年間は胃がん検診で内視鏡検査を受けるようにしましょう。
胃がん検診は50歳以上隔年に変更
胃内視鏡検査が選べるように
自治体が行う対策型胃がん検診は、2016年に受診推奨年齢と頻度が変更になり、「40歳以上、1年に1回のバリウム検査」から「50歳以上、2年に1回の内視鏡検査」の選択ができることとなりました。その背景には、現在の40代以下でピロリ菌感染者が減っていることがあります。また、正確にバリウム検査ができるレントゲン技師やバリウム検査の読影ができる医師が減ってきてしまったこともあります。
胃内視鏡検査は、内視鏡を口または鼻から挿入して胃を直接観察します。内視鏡を挿入する際に喉の痛みや違和感などを伴いますが、胃粘膜の微細な変化が鮮明に見えるため、早期の胃がんを見つけやすく、診断の正確性が高い検査です。バリウム検査を受けた方でも、「異常あり」と判定されたら、必ず精密検査(胃内視鏡検査)を受けましょう。
精密検査で胃がんと診断されたら、ステージ(がんの進み具合)やがんの性質、体の状態などに基づいて治療方法を選択します。胃がんのステージは、胃がんの深さ、胃の近くにあるリンパ節への転移の有無、遠隔転移の有無の組み合わせで決まります(図3)。
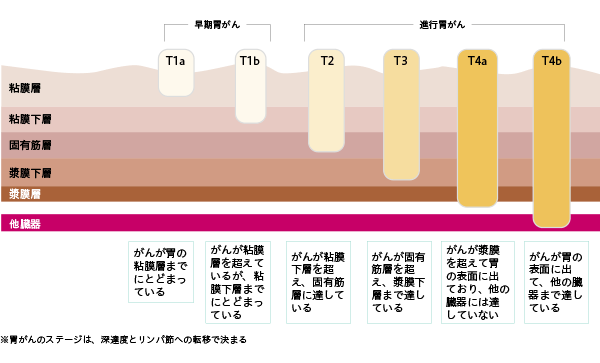 国立がん研究センター 各種がん101 胃がんより作成
国立がん研究センター 各種がん101 胃がんより作成
がんの「ステージ」と「グループ」を混同する人もいますが、「グループ」は病変の良性・悪性を示す5段階の分類で、がんが疑わしければグループ4、がんであればすべてグループ5となります。がんの進行度を示す「ステージ」は、さらに胃がんの深達度や転移などの精密検査をしてステージI〜IVが決まります。「グループ4(または5)です」と聞くと、末期がんだと思われる方もいますが、そうではありません。
早期胃がんは内視鏡治療が第一選択
ステージIの5年生存率は98%
胃以外の臓器やリンパ節への転移がなく、がんの深達度が粘膜層までの早期がんは、内視鏡治療(内視鏡的切除)が第一選択となります。内視鏡治療は手術に比べて体の負担が少なく、胃の機能も温存できます。入院は5日程度です。2016年以降、内視鏡治療の実数が手術を逆転し、胃がん全体の約6割を占めるようになっています。これは前述したように、2013年からピロリ菌感染慢性胃炎に対して、ピロリ菌検査および除菌前の半年以内の胃内視鏡検査(胃カメラ)が保険診療で義務づけられたことによって、小さな早期胃がんが多く発見されていることが理由として考えられます。
内視鏡治療の主流は、高周波ナイフで粘膜下層から病変をはぎ取るように切除する「ESD(内視鏡的粘膜下層剥離術)」です。がんの取り残しが少なく、再発も少ない治療法です。
胃がんが粘膜下層に達している場合は手術が推奨されます。切除する胃の範囲は、がんのある部位とステージによって決まります。ステージII・IIIの治療は、手術の前に抗がん剤を投与する「術前化学療法」が優先されます。手術のみよりも、術後の予後(見通し)が10%程度改善されると報告されているからです。切除する範囲など手術の内容は変わりませんが、手術前に化学療法を行うことで先々の転移を予防できていると考えられます。また、最近の手術の多くは腹腔鏡下手術であるため、従来の開腹手術と比べて術後の回復が早く、入院期間も短縮されています。胃がんの切除が難しく遠隔臓器への転移がある場合は、薬物療法などの治療法を検討します。
胃がんは早期発見すれば、ほとんど治すことが可能になっています。早期胃がんのステージIの5年生存率は約98%です(生存率は全生存率で計算するため他病死も含まれます。胃がんによる原病死はほとんどありません)。しかし、進行胃がんは転移の可能性を考慮しなくてはなりません。術前化学療法でステージII/IIIの予後は少し良くなりましたが、ステージIVの進行胃がんの予後はさほど改善されているわけではありません。だからこそ、胃がんは早期発見・早期治療が重要なのです。
胃がんを予防するには、胃がんの原因であるピロリ菌をできるだけ早い時期に除菌することが効果的です。繰り返しになりますが、まずピロリ菌検査で感染の有無を確認し、ご自身に胃がんのリスクがあるかを把握してください。感染していた場合は除菌し、定期的に胃がん検診を受けることをお勧めします。また、喫煙や塩分過多の食事といった胃がんのリスクを高めるような生活習慣は避けましょう。ピロリ菌に感染していなければ、胃がんのリスクは限りなく低いため、胃がん検診は受けなくても良いと言われています。
現在、日本胃癌学会では、患者向けの胃がんのガイドラインを作成しています。学会のウェブサイト(https://www.jgca.jp/guideline.html)で公開を予定していますので、こちらを参照するのも良いでしょう。
1992年東京医科大学医学部卒業後、国立がんセンター中央病院内視鏡部医長、国立国際医療研究センター病院消化器科医長・内視鏡科科長などを経て、2012年に東京医科大学医学部消化器内科学分野准教授。15年、日本大学医学部内科学系消化器肝臓内科学分野教授。日本発の内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)の開発と普及に貢献。日本胃癌学会(理事)、日本消化器病学会専門医・指導医、日本消化器内視鏡学会専門医・指導医など資格多数。