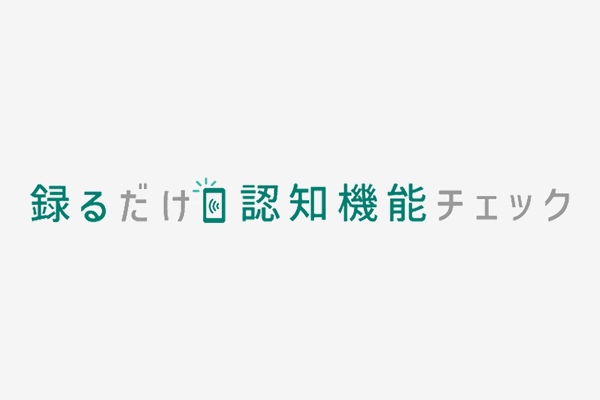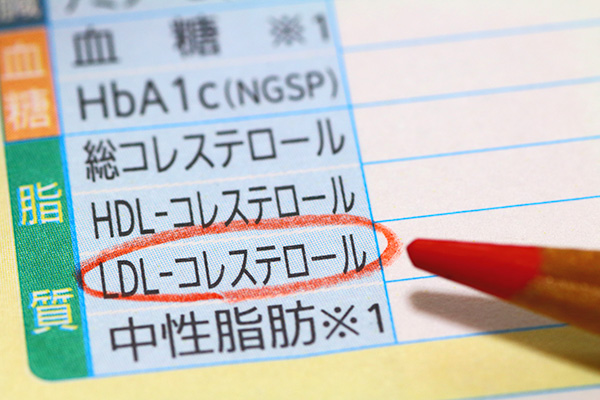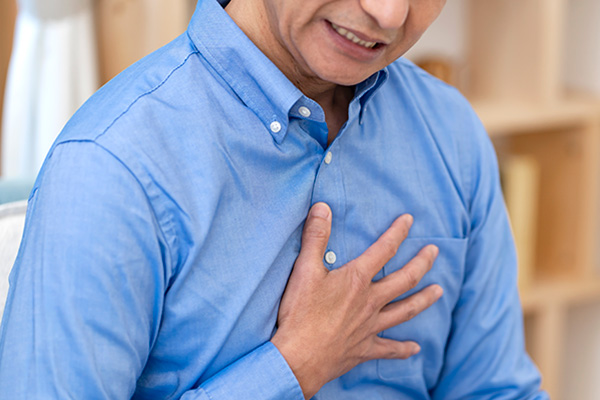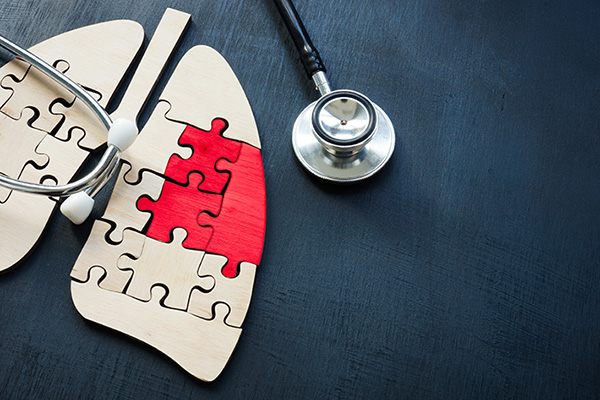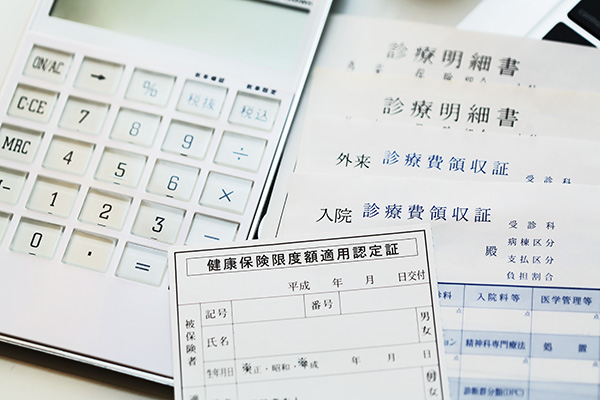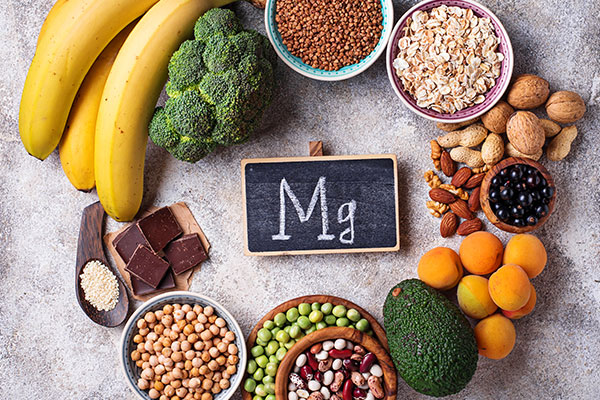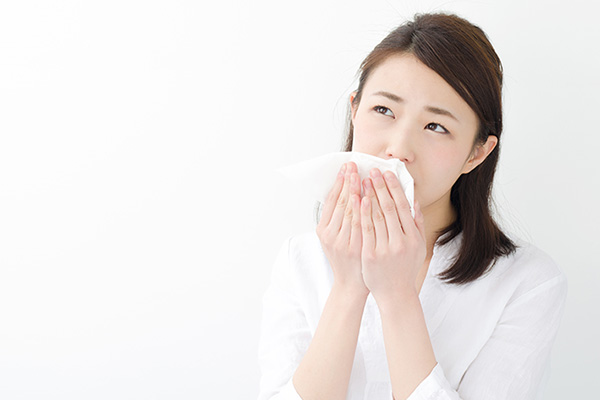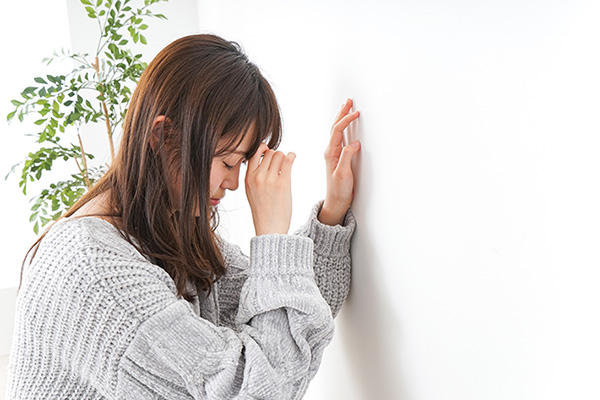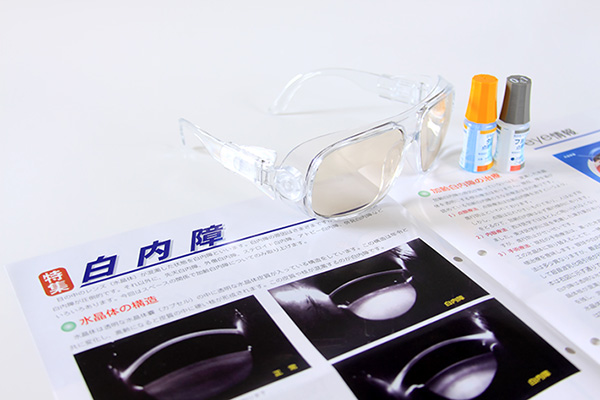年齢を重ねるとともに筋力が低下し、体力の衰えを感じることが増えていきます。しかし、原因は加齢だけでなく、普段の筋肉の使い方にもあると言われています。日常生活であまり使っていない“サボリ筋”とは何か、鍛えるためにはどんなトレーニングを行えばよいのか、理学療法士で日本身体運動科学研究所 代表理事の笹川大瑛さんに伺いました。
自分の身体年齢はどのくらい?
あなたは自分の体力に自信がありますか? まず、自分の筋力や体力を簡単にチェックできるテストを行ってみましょう。
試していただくのは「片足立ち」です。スマートフォンなどのストップウォッチをセットしてから、腰に手を当てて両目を閉じ、片方の足を上げてキープします。
軸足が動くか、上げた足が床につくまでの時間を計測します。
※片足立ちをする際には、障害物や平らな広い場所で無理せずに行いましょう。
下表の平均値を下回る場合は筋力や体力が低下し、身体年齢が実年齢よりも高くなってきている目安の1つになります。

出典:国立長寿医療センター研究所・老化に関する長期縦断疫学研究(第7次調査)より作成
一般的に男性は40代、女性は30代をピークに 筋力が低下する傾向にあります。「以前に比べて体力が落ちた」と自覚する機会も増える年代です。ただし、全身のすべての筋肉量が等しく減少するわけではありません。
実は、日常生活の動作や姿勢のクセなどによって、よく使われる筋肉とあまり使われない筋肉があり、最初に落ちていくのは、普段あまり使われていない筋肉なのです。
笹川先生は、前者のよく使われる筋肉を“ガンバリ筋”、後者のあまり使われない筋肉を“サボリ筋”と呼んでいます。さぼっている筋肉があると、必ずどこかにしわ寄せがいって、頑張る筋肉が出てきます。頑張る筋肉にばかり偏って負担がかかることによって、慢性的な腰痛やひざの痛みなどが生じやすくなります。また、運動などで急激に筋肉に負荷をかけたときにアキレス腱が切れたりするなど、ケガのリスクも高まります。
加齢によって低下した筋力は、運動や筋力トレーニングなどで強くすることが可能です。ただし、普段から偏った体の使い方をしていて、ガンバリ筋とサボリ筋の差が大きいと、負荷の大きいトレーニングはケガを引き起こす要因になります。例えば有効な筋トレとして知られるスクワットも、ひざを痛めることになりかねません ので気を付けましょう。
見落としやすい、足首周りのサボリ筋
体は、骨と骨との接合部分である関節によって動きます。筋肉は関節をスムーズに動かしたり、関節を締めて安定させたりする役割を担っています。関節を支える筋肉は決まっていて、1つの関節は2つの筋肉で支えられています。身体年齢を若く保つためには、次の6つの重要関節に関わる12のサボリ筋 をトレーニングすることが重要です。

この中でも、特に普段あまり運動していない人や体力の低下を感じている人が強化したいのが、「足首」を支えているのにサボリがちな筋肉である、
靴のかかとの外側がすり減っている、扁平足が気になる、ガニ股やО脚がひどくなってきた、といった場合は特に、偏った足首の使い方をしている可能性があります。足首の筋力が低下すると安定性が悪くなり、ひざでバランスを取ろうとして負荷がかかり、ひざの痛みを引き起こす原因になります。また、ちょっとした段差でつまずいて足を捻るなど、ケガのリスクも高まります。足首周りのサボリ筋を鍛えるために、下記の「10秒トレーニング」を行いましょう。
足首周りを鍛える10秒トレーニング
(ふくらはぎの内側に力を入れる)
- 1.床に座って片足を伸ばし、反対の足のかかとを、すねと床につける
骨盤を立てて背すじを伸ばして床に座り、手を後ろについて上半身の重みを支える。左足を前方へ真っ直ぐ伸ばしたら、右のひざを曲げ、かかとを左足のすねと床につけて、つま先を上に向ける。 - 2.かかとの位置はずらさずに、つま先を内側へ最大限に倒す
かかとの位置はずらさずに右足首を真っ直ぐに伸ばし、つま先を左足のほうに最大限倒した状態を10秒間キープする。次に、左右の足を入れ替えて同様に行う。1日1セット程度を行うと良いでしょう。


【ここに注意】
かかとが床から離れたり、つま先が反った状態で行ったりすると、
(すねの内側に力を入れる)
- 1.床に座って片ひざを内向きに立て、つま先を上げる
骨盤を立てて背すじを伸ばして床に座り、手を後ろについて上半身の重みを支える。右ひざを立てて軽く曲げてから少し内側に入れ、つま先を上に向ける。左足は楽にする。 - 2.ひざ、かかとの位置はずらさずに、つま先を床に向けて倒す
ひざ、かかとの位置はずらさずに、上げていた右足のつま先を倒して床につけ、親指の腹で床を押し、10秒間キープする。親指は、すねのラインから真っ直ぐの位置にする。次に、左右の足を入れ替えて同様に行う。1日1セット程度を行うと良いでしょう。


【ここに注意】
つま先が内側に倒れると、すねではなく、ふくらはぎの内側に力が入ってしまうので、親指をしっかり床につける意識を持ちましょう。また、床に倒すときに足指が反ると、ふくらはぎ全体に力が入ってしまうので、足指は軽く「グー」を握り、土踏まずが潰れるように踏みましょう。
ひざ周りを鍛える10秒トレーニング
さらに、ひざ周りのサボリ筋を鍛えると、ひざの痛みの予防効果や下半身の筋力アップ効果が高まります。
(太もも内側全体に力を入れる)
- 1.床に寝て両ひざを立て、片足のつま先を内側に向ける
両手のひらを上に向けながら、仰向けに寝て両ひざの間隔を5cmくらい開けて立て、右足のつま先だけを内側に向けて足指を「グー」に握る。 - 2.お尻を上げる
肩、ひじ、足の位置は動かさずに、両ひじ・両足のかかとを支点にして、お尻、腰、背中の下部を引き上げる。太ももの内側に力を入れた状態を10秒間キープする。次に、左右の足を入れ替えて同様に行い、1日1セット程度を目安に行うと良いでしょう。


【ここに注意】
両ひざの間隔が離れすぎたり、トレーニングする側のひざが内側に入ったりすると、太ももの内側ではなく、太もも裏やお尻の筋肉に力が入ってしまうので気を付けましょう。
(太もも内側の後ろ側に力を入れる)
- 1.床に座って片足のかかとを浮かせる
骨盤を立て、背すじを伸ばして床に座り、手を後ろについて上半身の重みを支える。左足を前方に伸ばし、右足のつま先を内側に向けてから足指を「グー」に握る。右ひざを軽く曲げて、かかとを少し浮かせる。 - 2.浮かせたかかとを床につけ、つま先をさらに内側に向ける
右足のつま先をさらに最大限まで内側に向け、その状態のままで浮かせていた右足のかかとで床を踏みつけ、10秒間キープする。次に、左右の足を入れ替えて同様に行い、1日1セット程度を目安に行うと良いでしょう。


【ここに注意】
足の裏が正面を向いたり、ひざを曲げ過ぎたりすると、太もも裏の外側の筋肉に力が入ってしまうので正しい姿勢を心がけてください。
次のような時にサボリ筋トレーニングを行うのは症状を悪化させる可能性があるので止めましょう。
- □ケガや骨折をしていて体を動かせない
- □炎症や腫れがあって少し動くだけでも痛みを感じる
トレーニング中に「つりそう」になるのは、サボリ筋にきちんと刺激が届いていることによる反応なので、そのままトレーニングを継続しましょう。2週間程度続けると、「以前より歩きやすい」「姿勢が良くなった」「腰やひざの痛みが改善した」といった効果を感じる人が多くなります。日頃から自分の体をチェックし、様子を見ながら無理せず続けていきましょう。
日本大学文理学部体育学科卒業。同大学大学院(教育学)修了。教育学修士。関節の動き、運動能力の向上やスポーツが上達する方法を科学的に研究する、運動科学の専門家。病院でのリハビリテーション経験や独自の研究を経て、“サボリ筋”を鍛える「関節トレーニング」を考案。関節痛の予防・改善のほか、アスリートの運動能力向上に貢献している。『運動能力が10秒で上がる サボリ筋トレーニング』(KADOKAWA)など著書多数。