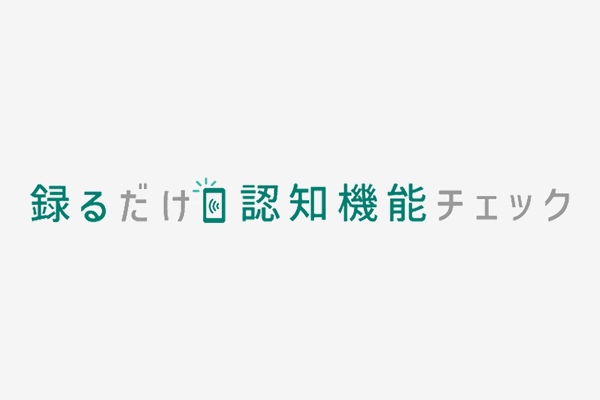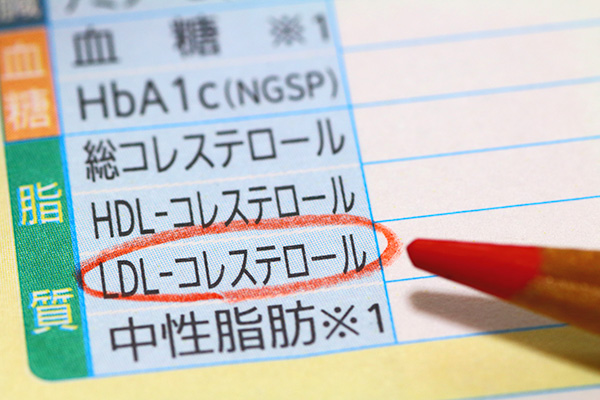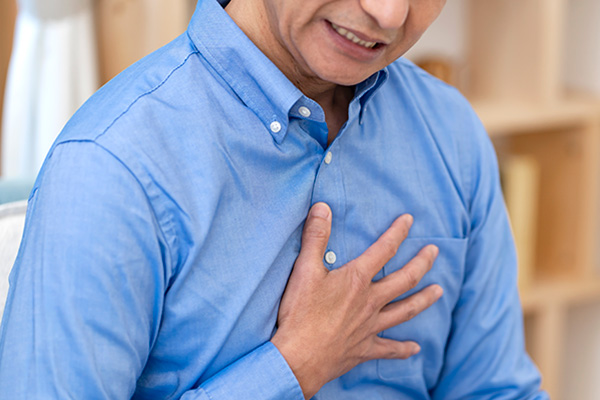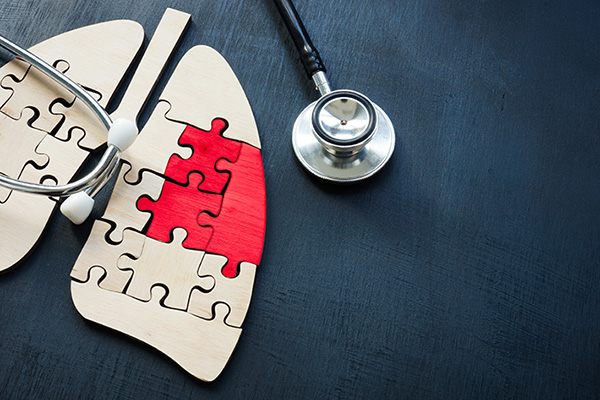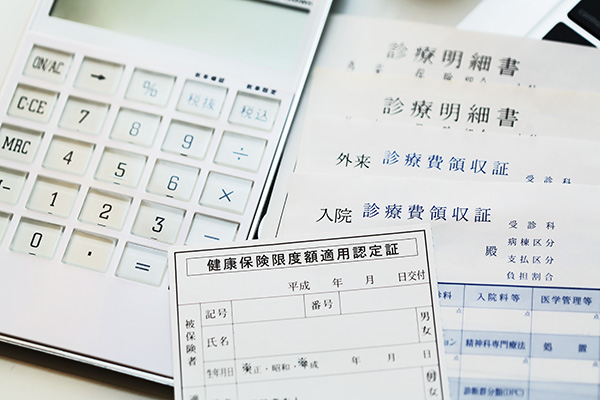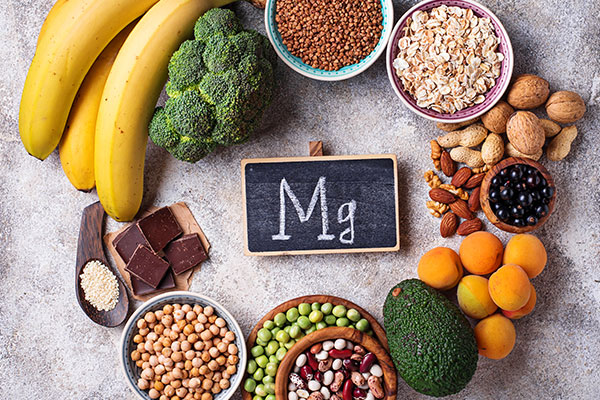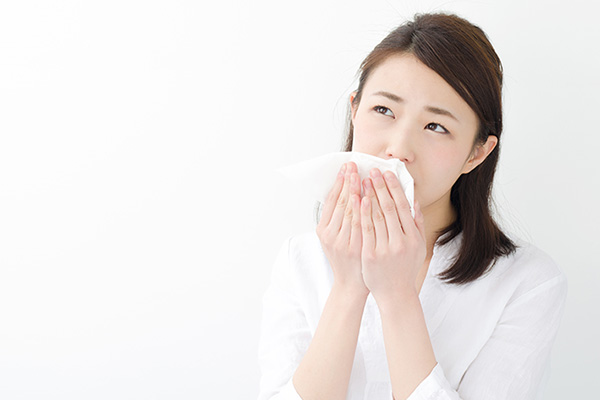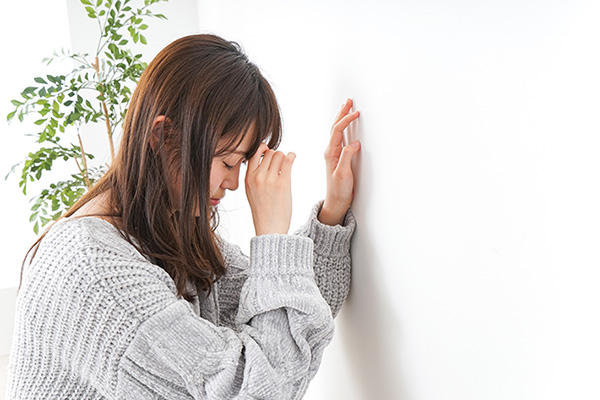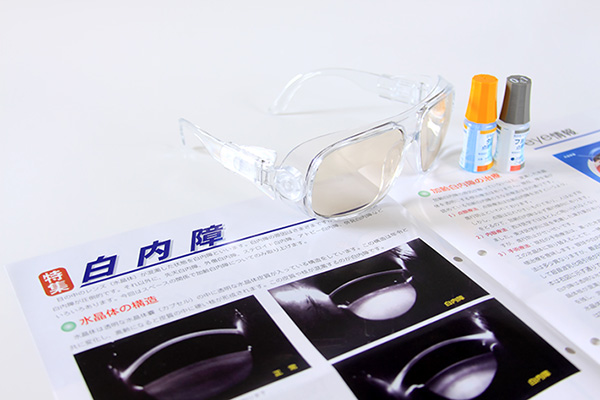近年、脳の機能に関する研究が進み、加齢による脳の変化などが明らかになってきました。その中で、脳は高齢になっても鍛えられることが分かってきています。何もしなければ年齢とともに衰えていくばかりですが、日々の生活習慣を見直すことで脳の若返りも期待できるとも言われています。脳の健康や若々しさの維持・増進につながる日常生活のポイントについて、東北大学加齢医学研究所 臨床加齢医学研究分野 教授の瀧 靖之先生に伺いました。
脳が老化するとは
~脳内で起きている変化~
年齢を重ねると「最近もの忘れが多い」「記憶力が低下した」と感じることが増えていきます。これは、加齢にともない脳の体積が減少するなど、脳でさまざまな変化が起こることが影響しています。
ヒトの脳は、20歳くらいをピークに萎縮しはじめ、体積が減少していくことが分かっています。脳の中でも特に加齢による萎縮が進みやすいのは、神経細胞が多く集まっている
一方で、脳の神経ネットワークに関わる神経線維(軸索)が多く集まっている

脳の老化を促進する4つの要因
瀧先生は研究において、5~80 歳までの約3, 000人に対して行った脳MRI検査の結果から大規模な脳画像データベースを作成し、脳の形態と機能、生活習慣、認知機能などの関係性を調べてきました。それらの研究から、脳の老化ともいえる、脳の萎縮や機能の衰えを促進するいくつかの要因が明らかになってきました。
その1つは「加齢」そのものです。歳を重ねるにつれて脳の神経細胞が減少するなど、脳が徐々に変化するためです。そのほかにも、脳の老化には主に4つの要因が関係していることが分かってきました。
- 1.喫煙
タバコを吸うと、全身の細胞への酸素供給が低下するほか、動脈硬化を促進します。その影響は脳細胞にもおよび、結果的に脳の萎縮を促進するといわれています。 - 2.飲酒
アルコールが代謝される過程で生成されるアルデヒドには毒性があり、長時間アルデヒドにさらされることが脳に影響します。特に、アルコールやアルデヒドの分解酵素の活性が低い、いわゆる“お酒が弱い人”は影響を受けやすいので注意が必要です。 - 3.肥満
肥満は喫煙と同様に動脈硬化を促進することから、酸素や栄養が細胞に行き届きにくくなり、脳を萎縮させるといわれています。女性に多い皮下脂肪型肥満に比べて、男性に多い内臓脂肪型肥満のほうが体内で慢性的な炎症を引き起こしやすく、より危険性が高いという特徴があります。 - 4.うつ
うつ病患者の脳では、記憶に関わる海馬 という領域の萎縮が見られるという報告があります。記憶力などをつかさどる海馬が萎縮することで、記憶力が低下したり認知症のような状態になったりする可能性があります。
脳の衰えを防ぐ生活習慣と脳を活性化する行動
脳の衰えを防ぎ、若々しくいられるようにするにはどうすればいいでしょうか。これまでに報告されてきた数多くの研究成果の中でも、信頼性が高い6つの方法についてご紹介します。
- 1.運動
脳の体積減少を抑えて、脳を健康に保つ方法として特に有効だとされているのが運動です。息が少し弾むくらいの中強度の有酸素運動を30分から1時間程度、週に2~3回行うことで脳の血液内の成長促進成分(脳由来神経栄養因子/BDNF:brain derived neurotrophic factor)が増え、脳の神経新生を促して海馬の体積が増えるという報告があります。筋肉トレーニングも有酸素運動と同様の効果があることが分かってきています。最近では、早歩きや階段上りなど、ジョギングほどの強度がない運動でも効果が期待できるといわれています。 - 2.趣味活動
好きな趣味に没頭したり、知的好奇心を持ったりすることが、認知機能の向上につながるという報告は多数あります。趣味を持つことで活動的になり、脳に良い刺激を与えて、脳の可塑性 (神経細胞のネットワークが変化して適応する力)を高めるといわれています。さまざまな趣味の中でも、可能であれば受動的な趣味より能動的な趣味がおすすめです。例えば、スポーツ観戦よりも自分自身でプレーする、音楽鑑賞よりも自分で楽器を演奏する、といったことが挙げられます。楽器演奏に関しては、健康な人が将来認知症になるリスクを下げるという報告もあります。 - 3.会話、他者とのコミュニケーション
会話をすることは、相手の表情や仕草を観察して、相手の考えを理解したり想像したりすることで、自分の気持ちをどう伝えるか考える、といったことを瞬時に行う行為です。表情の認知、感情や言語の理解、共感性、社会性などに関わる脳のさまざまな領域を駆使することにもつながります。メールなどの文字でも会話はできますが、対面での会話のほうが脳のさまざまな領域を使うことになるので、脳の健康にとってはより良いといえます。 - 4.バランスの良い食事
最近の研究では、特定の何かを食べるよりもバランスよく多品目を食べることの重要性を示す研究成果が目立っています。その理由の1つに、腸内細菌叢 の多様性があります。近年、腸と脳が互いに影響しあう“腸脳相関”の研究が盛んに行われていますが、特定のものばかり食べることで腸内細菌叢の多様性が損なわれ、認知機能にも影響することが分かってきています。脳のことを意識して食事をするなら、和食や地中海食※1に代表されるような、低カロリーで良質なたんぱく質が豊富な食事がおすすめです。肉よりも魚を中心に、野菜や豆類などが多く含まれているとさらに良いでしょう。 - 5.十分な睡眠
睡眠は単に疲れをとるためだけではなく、記憶の保持・定着や脳内の老廃物を洗い流す、という脳にとって極めて重要な働きがあります。特に後者が重要で、アルツハイマー型認知症の原因物質とされているアミロイドβというたんぱく質のゴミは、眠ることで脳から洗い流されるといわれており、その時間が十分でないとゴミの蓄積が進んでしまいます。脳内の老廃物を洗い流すには6時間以上の睡眠が必要といわれていますので、睡眠時間をしっかり確保することが大切です。 - 6.幸福感、ポジティブな感情
最近の研究では、人生や生活に対する満足感や幸福感などのポジティブな感情が認知症リスクを下げるという結果が報告されています。その理由としては、楽しさや幸せを感じることでストレスレベルが下がり、それにより高血圧や糖尿病をはじめとする生活習慣病、動脈硬化のリスクも低くなり、結果として脳や全身の健康維持につながると考えられているためです。ささやかなことでもいいので、日々の生活の中で、「幸せだな」「楽しいな」と思えることを意識するとよいでしょう。
※1 地中海沿岸の国々の人が食べている伝統的な料理。オリーブオイル、ナッツ、豆類、全粒粉など未精製の穀物をよく使い、果物や野菜、魚を多く使う。食事の際に適量のワインを飲むことが特徴。
何歳から始めても手遅れということはない

ここで紹介した6つの項目のうち、運動、睡眠、食事という3つは生活習慣病予防と共通しています。脳の衰えや認知症には加齢の影響もありますが、生活習慣との関わりも大きく、高血圧や糖尿病血糖値をコントロールすることにも似ています。趣味、会話、幸福感など、自ら行動を起こすことで脳に刺激を与えることになります。
大切なことは、今の年齢に関わらず、思いついたその日その瞬間から、脳の健康を意識した生活を始めることです。20代、30代の人に「将来の認知症リスクを低減するために生活習慣を変えよう」と訴えても意識しにくいとは思いますが、中高年になってからいざ運動習慣を身につけようと思っても難しいので、早いほうが始めやすいというメリットがあります。
70歳、80歳からでは手遅れということもありません。脳には
1993年東北大学理学部卒業、同年東北大学医学部入学。2003年東北大学大学院医学系研究科博士課程修了。東北大学助手、助教、准教授を経て、12年より東北大学東北メディカル・メガバンク機構教授、13年より現職。大規模脳画像データベースを用いて、脳の発達、加齢を研究し、どのような生活習慣が脳の加齢を抑えるかを明らかにしてきた。主な著書に『本当はすごい早生まれ』(飛鳥新社)、『脳医学の先生、頭の良くなる科学的な方法を教えてください』(日経BP)などがある。