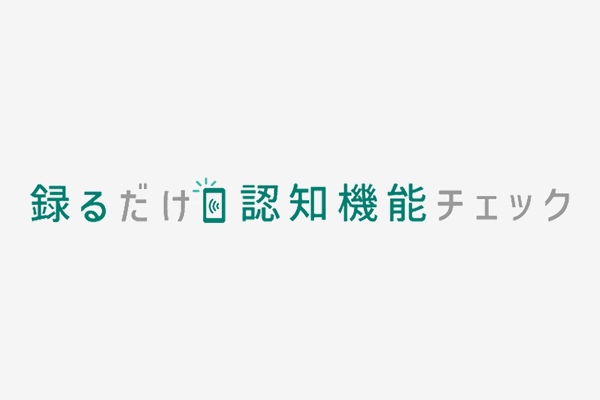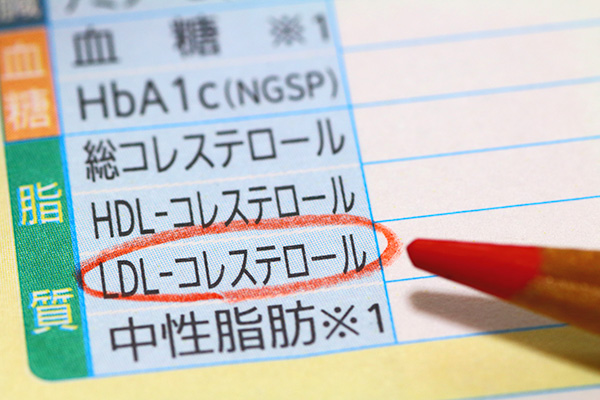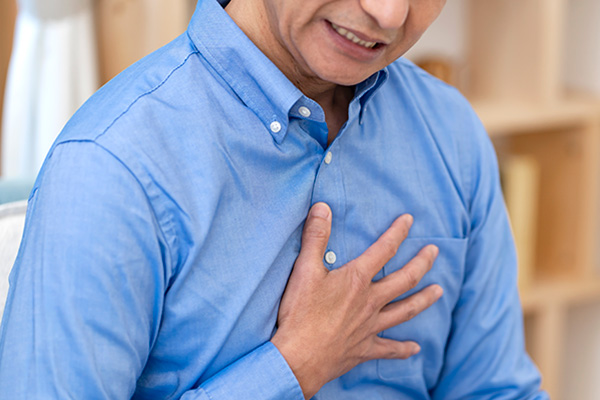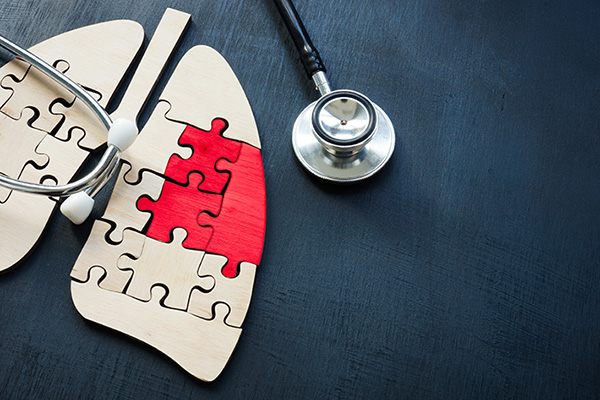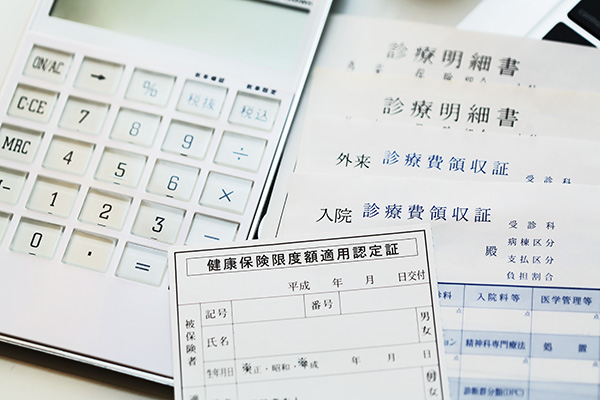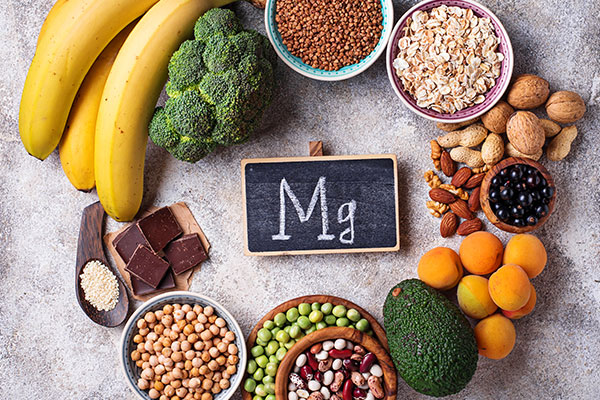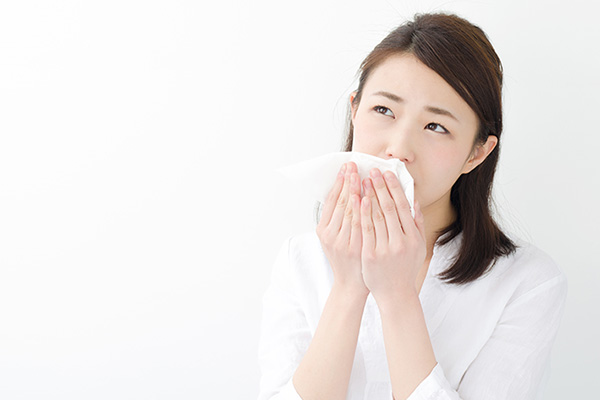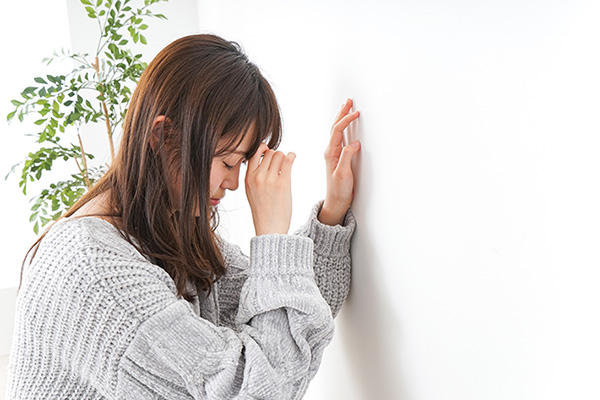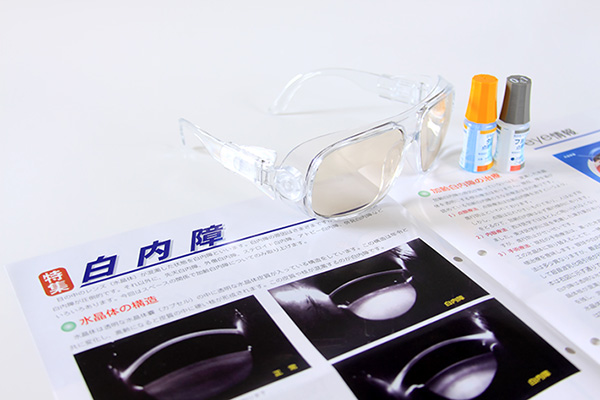誰でも気軽に取り入れやすい運動として人気のウォーキング。しかし、毎日のんびり散歩すればよいと思う人もいれば、「1日1万歩以上歩かないと効果がない」と考える人もいるなど、歩き方に対する認識はさまざまです。そこで、今回は「健康に長生きするための歩き方」について25年にわたり研究を行う、東京都健康長寿医療センター研究所「中之条研究」部門長(運動科学研究室長)の青栁幸利先生にお話を伺いました。
生活習慣病を防ぐ最適な歩数と歩き方
生活習慣病の予防や改善は、健康に長生きするための大きな課題の1つです。特に代表的な病気である「高血圧症」「脂質異常症」「糖尿病」は放置すると動脈硬化が進行し、脳卒中や心筋梗塞などの深刻な病気のリスクを高めます。これらは「生活習慣病の三大要因」と言われますが、「糖尿病」は進行すると網膜症や腎症、神経障害の3大合併症を引き起こし、健康寿命を短くする要因となります。
この「高血圧症」「脂質異常症」「糖尿病」の予防や改善には、「1日8,000歩/速歩き(中強度活動)20分」が最も効果的であることが、東京都健康長寿医療センター研究所の「中之条研究」で分かりました。同研究は、群馬県吾妻郡にある中之条町の65歳以上の全住民5,000人を対象に、2000年から次のような方法で行われています(現在も継続中)。
- 1.対象となった5,000人に、日常生活の運動頻度や時間、生活の自立度、睡眠時間、食事などに関するアンケートを実施
- 2.1.のうち2,000人に、血液検査や遺伝子解析を実施
- 3.さらに2.のうち1,000人に、身体活動量計(歩数と活動強度を測定する機器)を24時間、365日装着してもらい、身体活動状況を把握
同じ地域の住民を毎日連続して25年以上にわたって調査したことで、1日の歩数と中強度活動時間に対する病気の予防効果が明らかになりました。
 出典:青栁幸利「すべての病気が防げる長生き歩き」(エクスナレッジ)
出典:青栁幸利「すべての病気が防げる長生き歩き」(エクスナレッジ)
上のグラフが示す通り、歩数と中強度活動時間が増えると、予防できる病気も増えます。同研究ではこの結果から、「1日8,000歩のうち、速歩き(中強度活動)を20分行うと、生活習慣病の予防効果が得られ、健康長寿につながる」という最適解を導き出しています。
速歩き(中強度活動)の目安を知ろう
大事なポイントは、ただのんびりと8,000歩程度散歩をするのではなく、「速歩き(中強度活動)20分」をその中に入れることです。20分連続して歩く必要はなく、10分を2セット、あるいは5分を4セットというように分割して行っても病気の予防効果は変わらないことが中之条研究から分かっています。
ちなみに「中強度活動」とは、「これ以上続けることができない」といった全力の状態を最大強度活動とした場合の半分程度の強度の活動を指します。
自分にとっての速歩き(中強度活動)を知るため、次の方法を試してみましょう。
息が切れてもなんとか会話ができる程度の速歩きを意識して、1分間あたり120歩(1秒間に2歩)のペースで3分以上歩く。
その際に
- □鼻歌が歌えるなら→低強度
- □息が切れてもなんとか会話ができる程度なら→中強度
また、身体活動の強さを表す単位「メッツ」についても知っておくと、日常生活の中での中強度活動の目安になります。「メッツ」とは、座って安静にしている状態「1.0メッツ」を基準とし、身体活動によってその何倍のエネルギーを消費するかを示すもので、例えば普通に歩く(15分で1kmのペース)場合は「3.0メッツ」となります(下表参照)。
中強度活動は「4.3メッツ」から「6.0メッツ」未満に当たります。
 出典:厚生労働省「健康づくりのための身体活動・運動基準2023」より抜粋引用
出典:厚生労働省「健康づくりのための身体活動・運動基準2023」より抜粋引用
掃除機かけや風呂掃除など、1日の日常生活の中で中強度活動を20分行っているなら、それとは別に速歩きをする必要はありません。
自分が1日20分の中強度活動を達成できているのかを客観的に把握するには、歩数だけでなく中強度活動も計測できる市販の身体活動量計を身につけるのがおすすめです。価格は数千円程度のものが多く、スポーツ用品店や家電量販店、インターネット通販などで購入できます。
忙しくても1日8,000歩を達成するには
デスクワークが中心で、外を歩く時間をあまり取れない人にとっては、1日8,000歩はハードルが高いと感じられるかもしれません。しかし8,000歩の中には、家や職場の中での歩数も含まれます。まずは前述の身体活動量計やスマートフォンの歩数計アプリで、室内をどのくらい歩いているのか調べてみましょう。家事を多く行っている人などは、意外に歩いていることが分かるはずです。室内での歩数と併せて、外での歩き(そのうち20分速歩き)で8,000歩達成を目指しましょう。
また、毎日コンスタントに「1日に8,000歩/速歩き(中強度活動)20分」を実践しなくてはならないわけではありません。天気が悪い、疲れ過ぎて歩く気力が湧かないなど、さまざまな理由から1日に8,000歩に届かない日もあるでしょう。その場合は翌日多めに歩くなどして調整し、1週間の平均で「8,000歩/速歩き(中強度活動)20分」を達成できればOKです。身体活動量計は1週間の平均値を把握するという点でも役立ちます。
体力の問題などで「8,000歩/速歩き(中強度活動)20分」が難しい場合は、次のように3段階でレベルを調整すると良いでしょう。
 出典:青栁幸利監修「中之条研究20年のまとめ 健康長寿の秘訣は“歩き方の黄金律”にあった」(一部改変)
出典:青栁幸利監修「中之条研究20年のまとめ 健康長寿の秘訣は“歩き方の黄金律”にあった」(一部改変)
将来寝たきりにならないためにも、少なくとも1日2,000歩以上は歩くようにしましょう。10分ほどの外出(1,000歩程度)に、家事などの作業をプラスすると2,000歩に相当する活動量になります。
なお、かつては心臓病など運動が禁忌とされる病気もありましたが、現在は医学的に歩いてはいけない病気はほとんどないと言われています。持病がある人も、無理のない範囲で歩く習慣を付けましょう。
一方、体力に自信があると「8,000歩以上、余裕で歩ける!」と、1万歩でも2万歩でも張り切って歩く人もいますが、過度の運動は免疫機能を低下させ、感染症を引き起こす要因になります。風邪を引きやすいといった自覚症状がある人は特に、8,000歩を基準として歩きすぎないようにしましょう※。
※参考:Habitual physical activity and immunological function in older individuals:Preliminary findings from the Nakanojo study
歩幅を10cm広げて大股で歩く
速歩きの目安は前述の通り「息が切れてもなんとか会話ができる程度の速さ」です。具体的な歩き方は、下記のフォームを参考にしましょう。

意識したいのは、普段より10cm程度歩幅を広げて「大股で歩く」ことです。歩幅を広げて大股で歩くと、自然と背筋とひざが伸び、腕を大きく振るようになります。良い姿勢とダイナミックな体の動きに伴ってピッチが上がり、歩くスピードが上がります。
靴はウォーキング用のものでも、スニーカーでも、自分の足に合って歩きやすいものであればOKです。できれば少しつま先にゆとりのあるサイズを選び、靴ひもで締め加減を調整すると、より足にフィットしやすくなり、足への負担の軽減につながります。
起床直後はNG、夕方がおすすめ
歩くことを健康維持や病気予防につなげるためには、歩くタイミングも大切です。避けたいのは「朝起きてすぐ(30分以内)の歩行」です。
起床直後は体が休息モードで、自律神経の副交感神経が優位な状態にあります。活動モードの交感神経に切り替わるのには30分程度かかるので、その前に運動すると、血圧や心拍数が急上昇し、心筋梗塞などの心臓発作のリスクが高まります。
また、起きたときは脱水状態になっています。脱水も心臓発作を引き起こす要因の1つです。起床後すぐに水分補給をしても、体に吸収されるまではやはり30分程度かかります。これらの理由から、起床後30分以内のウォーキングは避けましょう。
逆に、おすすめの時間帯は夕方です。夕方に歩くことで血流がよくなり、体温が上がると、皮膚表面から熱を逃がす機能(熱放散)が働き、深部体温(体の中心部の温度)が下がりやすくなります。深部体温は睡眠の質に大きく関係していて、深部体温が下がることでスムーズに眠りにつきやすくなります。
寝付きの悪さや眠りの浅さに悩んでいる人は特に、夕方のウォーキングがおすすめです。会社帰りに少し遠回りして速歩きするなど、毎日の生活の中で夕方歩く時間をつくるとよいでしょう。
「1日8,000歩/速歩き20分」を継続すると将来的な健康長寿につながるだけでなく、短期的にも健康診断の数値が改善したり、体力がついて疲れにくくなったりするなど、さまざまな効果が期待できます。
まずは2カ月を目標に続けていきましょう。
医学博士。筑波大学卒業。1996年、トロント大学大学院医学系研究科博士課程修了。カナダ国立環境医学研究所温熱生理学研究部門、奈良女子大学生活環境学部および大阪大学医学部などを経て現職。群馬県中之条町に住む65歳以上の全住民5000人を対象とする疫学調査(中之条研究)を25年にわたって実施し、そこから「病気にならない歩き方の黄金律」を導き出したことで知られる。『すべての病気が防げる長生き歩き』(エクスナレッジ)など著書多数。